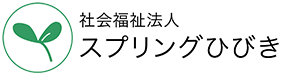放課後等デイサービス奏
社会生活を学ぶ場

生活能力向上のために、日常の基本動作を身につけられるような療育や訓練を行なっています。
また、社会の中で様々な体験をする機会を提供し、疑似体験などを屋外活動で活かすことで活動の幅を広げています。
サービスの内容
- ・食事や排泄、更衣など必要に応じて介助します。
- ・学校以外での社会生活のルールや、学年の違う利用者同士の関係づくりなどの療育をします。
- ・室内でできるレクリエーションや創作活動、外出など、日中活動の機会を提供します。
- ・送迎サービスは、平日の学校終了後のみですが、お気軽にご相談ください。
1日の過ごし方(月〜金曜)14:00~17:30
-送迎車にて学校へお迎え-
- 15:00〜 : 健康チェック・水分摂取・おやつ
- 15:30〜 : 個別療育or自由活動(花の水やりや観察、遊具を使った遊び、機能訓練士による訓練など)
- 17:00〜 : 身支度
- 17:30〜 : 送迎車またはお迎えにて帰宅
1日の過ごし方(土曜・長期休暇)10:00~16:00
-保護者送迎にて来所-
- 10:00〜 : 健康チェック・水分摂取・始まりの会
- 10:30〜 : 個別療育or自由活動(生活介護にてプルーン作業の体験、ごっこ遊びや散歩など機能訓練士による訓練)
- 12:00〜 : 昼食(持参or外注弁当)口腔ケア
- 13:00〜 : 休憩
- 14:00〜 : 個別療育or自由活動
- 15:00〜 : 水分摂取、おやつ
- 15:20〜 : 終わりの会
- 15:30〜 : 身支度
- 16:00〜 : 保護者お迎えにて帰宅


放課後デイサービス奏の概要
| 名称 | 放課後等デイサービス奏 |
|---|---|
| 住所 | 佐賀市高木瀬町大字長瀬196-3 |
| TEL | 0952-97-7200 |
| FAX | 0952-97-9175 |
kanade@spring-hibiki.com | |
| 定員 | 5名 |
| 対象 | 重症心身障害児 |
| 送迎 | 平日は学校へお迎え、ご自宅に送迎いたします。 |
| 開所日時 | 月曜日~土曜日(日・祝日は休み) |
| 料金 | [サービス費] 障害児通所給付費 [活動費等] 実費 |
当法人では365日24時間ケアを行なっております。
- ●卒業後は、法人内の生活介護・就労継続支援B型の利用が可能です。
●在宅サービスでは、入浴支援・移動支援・行動援護・移送サービス等が利用可能です。
●グループホーム利用にあたっての相談に応じます。